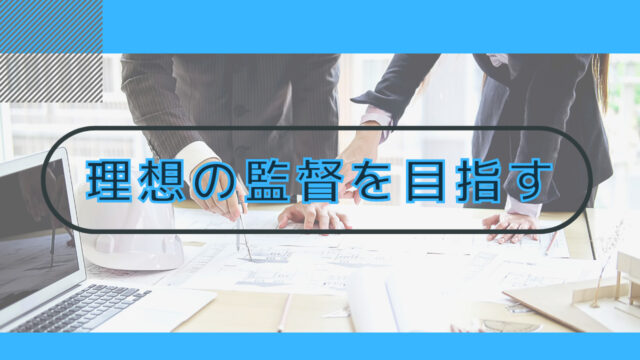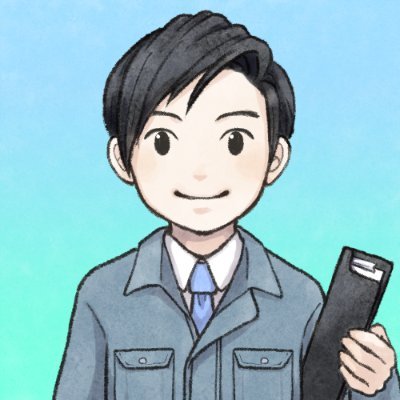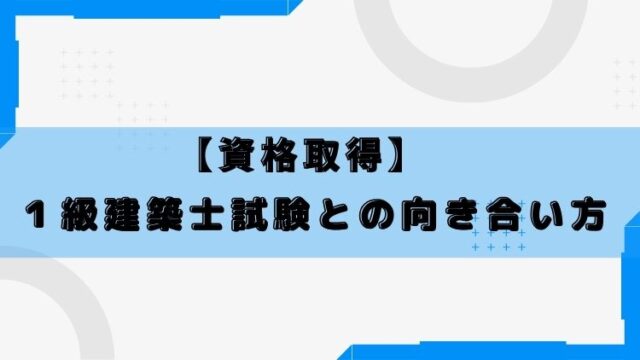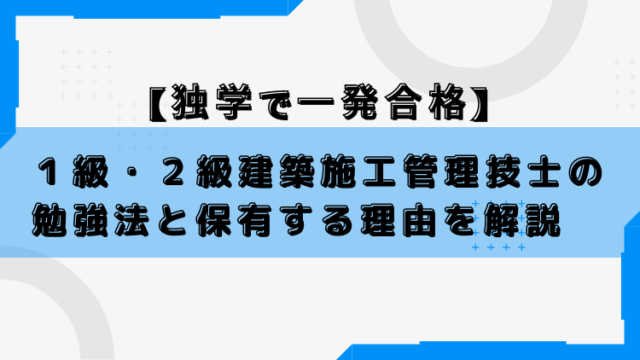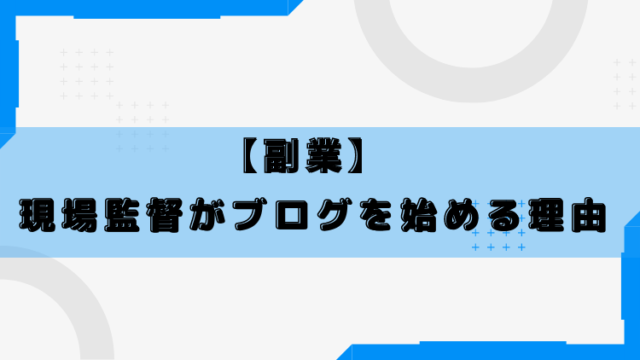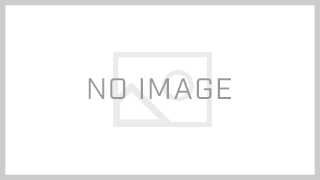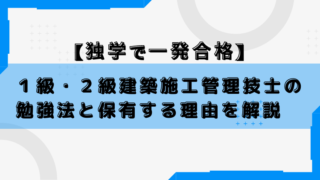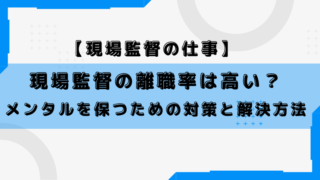どの資格学校が受かりやすいか?
わたしが勉強前に調べていたことです。
結局、自分にとって最適な資格学校が選べたかは分かりません。
でも、他人の意見ではなく、自ら選択したので後悔はありません。
どの資格学校を選んでも間違いではないと思います。
メリット、デメリット双方を天秤にかけ、ぜひ自分の意思で決めてみてください。
・なんちゃってストレート合格(2023年学科合格、2024年製図合格)
・社会人18年目
・合理主義
・取捨選択が得意
・嫌いなもの 何かを探している時間
一級建築士試験。
わたしは合格に至るまで、家族を犠牲にて勉強しました。
仕事、家庭、勉強、プライベート。
全てをバランスよくやり切れるほどこの試験は甘くはありません。
それでも支えてくれる人たちに試験のことを理解してもらい、
自分自身にとって適切な選択をできるための一助となるように記事を書きます。
2023年の製図は一度スルーして、なんちゃってストレート合格を果たしました
・最終目標設定をする
・最適な勉強方法を知る
目標設定について
わざわざ確認するほどの内容?
合格を目指さない人なんているわけがない
目標設定?そんなの試験に受かること以外ないでしょ
それって本当ですか?
わたしは受験時に本当にみんな同じ目標なのか疑問に思うことがありました。
なぜなら、重要なことを軽視し、細かいことの議論している場面を多々見かけたからです。
ここで、改めて。
目標は何でしょうか。
同じ目標を持つ仲間を見つけること?
資格学校の先生になること?
業務で役立つ知識を試験を通じて増やすこと?
大半の受験生は、この試験に合格すること、だと思います。
癪に触る方もいると思いますが、はっきりと言います。
例えば、カレーを作ってください
とお願いされたとします。
これが課題の条件です。
この課題に対して、ハヤシライスを作ろうとする人が一定数いるということです。
1番重要なことをスルーして、その人たちは隠し味に何を入れるか。
そんな話に夢中になっているように聞こえました。
過年度生たちが隠し味の話をするのはわかります。
ただ、初受チームが隠し味は何を入れただの、辛さにこだわりを持つだの、的外れでしかありません。
とにかく、まずはカレーを作るのです。
見た目と味に磨きをかけるのはカレーを作ることができた後の話です。
冗談抜きで1つのミスが死につながる残酷な試験です。
一級建築士試験において、肝は間違いなく法規です。
斜線・面積など、法に触れる内容は図面を見て一目瞭然。
残酷ですが、1万という数を超える図面を効率良く不合格にしていく作業。
法規ミスはそんなに採点方法にピッタリだとも思います。
だから、容赦無く切り捨てていく。
1発アウトだけはしないチェック体制を整え、全集中しましょう。
威張れることではありませんが、わたしは完璧な図面を書くことはできません。
交換添削のときも周りの受験生に褒められたこともほとんどありません。
でも、不合格にできない図面を書くことは得意だと思っています。
人にすごいと思われなくてもいいから、合格したい
そう思い続けて、勉強を続けてきました。
そうすれば自ずと勉強方法は定まってきます。
あなたの最終目標は何ですか?
自分に合った勉強方法を知る
効率的な勉強方法を知りたい。
わたしも常々思っていたことです。
結果、そんなものは存在しない。
余計なことに時間を使わず、問題を解きましょう。
詳しく説明していきます。
まず、根本的に合格への近道は存在しません。
厳密に言うと効率的な方法はあります。
(忘却曲線とか記憶定着しやすい時間とか)
ただ土台となるものがあってからこその話です
その土台とは、圧倒的な勉強量です。
こんな話を聞いたことがあります。
とある難関資格で最高得点で合格した方がいます。
その方に勉強のコツを聞く人は後を絶えないそうです。
最高得点で合格した方曰く、
勉強のコツを聞いてくる人たちはとにかく勉強しない。
要するに作業量が足りていないのだそうです。
最短距離を考える前にあれこれ考える時間があるのであれば、過去問を1つでも解け
ということです。
イチローも言っています。
小さなことを積み重ねることが、とんでもないところへ行くただ1つの道。
それならばガムシャラに問題解きます!
隙間時間フル活用します!
記憶定着のために寝る前もやりますわ
とにかく問題数をこなすことは必須です。
その上で。
次に計画性です。
優秀な頭の(かなり)良い先輩の言葉です、
資格合格に必要な要素は、危機感、やる気、計画性。
わたしが特に重要だと思うのは計画性です。
1日に費やすことのできる学習時間は?
週平均学習時間は?月平均学習時間は?
自分のライフスタイルに合わせ、まず無理のない計画を立てます。
私は学科800h、製図300h(課題発表後)を目標にし、試験日から逆算して勉強を始めました。
資格学校の宿題も膨大な量となります。
周りのライバルたちはその宿題をこなしてきます。
無理のない学習スケジュールに合わせて資格学校を選んでみてください。
資格学校選び
お待たせして、すみませんでした。
受験仲間の感想、勉強用で2年間SNSを活用し得た情報からメリット・デメリットをまとめます。
個人的な感想も含まれますので、あくまで学校選びの参考にしていただければ幸いです。
学科試験は資格学校ごとの合格率に差はさほど無いそうです
そのため、製図試験に絞って情報をまとめました
総合資格学院
メリット
・資格学校最大手
・教材のクオリティが高い (個人的に1番分かりやすかった)
・圧倒的な作業量による作図スピードアップ
・受講生が多いため、モチベーション維持しやすい
・受験生も多いが合格者数も多い
デメリット
・費用が高い
・課題数が多いため、仕事をしながら通学することが大変
・感覚的にストイックな人が多く、心が折れて離脱する可能性が否めない
・直前講座で追加費用が発生する
体育会系でストイックというイメージです
自分自身のペースメイクが苦手で、短期間で仕留めたい方向け
日建学院
メリット
・課題数が多く、総合資格さんより数十万コストが安い
・受講生が多いため、モチベーション維持しやすい
・直前講座のようなものは無く、追加費用無し
デメリット
・費用が高い
・後半の課題が難易度が高すぎて心が折れる
・2024年度の課題に関しては、過去問の内容を詰め込んでいるものが多く、良問とは言えない課題が多かった印象
総合資格さんとTACさんを足して2で割ったイメージです
TAC
メリット
・費用が他社と比較すると圧倒的に安価
・仕事をしながら通学する人にとって課題数が適切
・自発的に動ける人にとってはコスパ良し
デメリット
・自ら積極的に質問しないと理解力が向上しない
・他の資格学校と比べ課題が少ないので、作図スピードに差がつく
わたしはTACさん(長期)で合格することができました
個別指導塾
メリット
・自分にあった先生を選ぶことができる
・コストが大手資格学校に比べて抑えられる
デメリット
・自ら勉強のペースメイクをする必要がある
・WEB上でのやり取りとなり、タイムリーな質疑応答ができない
個人塾を選ぶ判断基準がなく、先生との相性の良し悪しに左右されそうです
そのため、ギャンブル性が少し高いと感じてました
独学
メリット
・コストを抑えることができる
・実際に独学で受かっている人もいる
デメリット
・情報収集が大変
・合格までのレールを自分で敷く必要がある
地頭の良い上級者向けという感じです
実際受かっている人も知っているのですが、私には真似できません‥
合格者に聞けば、通っていた学校のことは褒め、
不合格者に聞けば、通っていた学校の不満を言う。
これがSNS上で情報発信されている真実だと思います。
転職活動を定期的にしていますが、この資格がプラチナチケットであることは間違ありません。
かといって、人生全てを捧げるほどの資格でもないと感じています。
大手資格学校さんの場合は数ヶ月分の給料を支払って学びます。
メリットとデメリットを理解し、悔いの無い選択ができますように。
資格学校選びについて、個人的には迷っている時間がもったいない!
と思ってしまうので、まずは資料だけでも取り寄せてみてください。
初めは最大手の総合資格さんで宜しいかと。
さいごに
わたしは運良くなんちゃってストレート合格を果たすことができました。
正解だったとは言いませんが、思考や試験の向き合い方、勉強方法は間違っていなかったと確信しています。
努力が結果として現れない人たちとも話しました。
冗談抜きで残酷で過酷すぎる試験です。
この試験は人生の転機になり得る大切なもの。
それでも、最も大事なことはあなたを支えてくれる大切な人たちです。
試験のことを理解してもらい、自分や周りの大切な人にとっても適切な選択ができますように。
険しい道を選んだ勇敢な人たちが、最善の選択ができるように参考にしてもらえれば嬉しいです。
同志を応援しています。